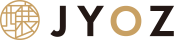column

日本でも栽培可能?栄養価は?ルピナス豆の可能性-東北大大学院・佐藤教授に聞く【後編】
痩せた土地でも力強く育つルピナス豆。地中海沿岸地方と南北アメリカ、南アフリカなどに200種以上が分布する豆で、ハッコウホールディングス社が日本で初めて、ルピナス豆の低アルカロイド品種の開発に成功しました。大豆と同等のタンパク質量を有する一方で、窒素肥料がほとんど不要というだけでなく、大豆の3分の1という非常に少ない水の量で育つという特性を持ち、大豆特有の臭み・クセがなく、大豆アレルギーのアレルゲンを持たないため多くの大豆製品の代替としても活用できるとして期待されています。 前編に引き続き、東北大学大学院の佐藤修正教授に、ルピナス豆の可能性についてお話を伺いました。
日本でも栽培可能?栄養価は?ルピナス豆の可能性-東北大大学院・佐藤教授に聞く【後編】
痩せた土地でも力強く育つルピナス豆。地中海沿岸地方と南北アメリカ、南アフリカなどに200種以上が分布する豆で、ハッコウホールディングス社が日本で初めて、ルピナス豆の低アルカロイド品種の開発に成功しました。大豆と同等のタンパク質量を有する一方で、窒素肥料がほとんど不要というだけでなく、大豆の3分の1という非常に少ない水の量で育つという特性を持ち、大豆特有の臭み・クセがなく、大豆アレルギーのアレルゲンを持たないため多くの大豆製品の代替としても活用できるとして期待されています。 前編に引き続き、東北大学大学院の佐藤修正教授に、ルピナス豆の可能性についてお話を伺いました。

ルピナス豆と共生する根粒菌の可能性とは?東北大大学院・佐藤教授に聞く【前編】
地中海沿岸地方や南北アメリカ、南アフリカなどに200種以上が分布し、大豆と同等のタンパク質を持ちながら、窒素肥料をほとんど必要とせず、使用する水も大豆の3分の1で済む「ルピナス豆」をご存じでしょうか? この環境負荷の低い作物は、大豆アレルギーのアレルゲンを含まず、代替食品としての可能性も秘めています。さらに、地球温暖化の要因となるCO₂やN₂Oの削減に取り組むマメ科植物の一つとして、研究が進められています。 豆発酵食品「醸豆(JYOZ/ジョウズ」を開発・製造・販売する「ハッコウホールディングス」とルピナス豆の研究を行っている、東北大学大学院の佐藤修正教授と番場大助教にお話を伺いました。
ルピナス豆と共生する根粒菌の可能性とは?東北大大学院・佐藤教授に聞く【前編】
地中海沿岸地方や南北アメリカ、南アフリカなどに200種以上が分布し、大豆と同等のタンパク質を持ちながら、窒素肥料をほとんど必要とせず、使用する水も大豆の3分の1で済む「ルピナス豆」をご存じでしょうか? この環境負荷の低い作物は、大豆アレルギーのアレルゲンを含まず、代替食品としての可能性も秘めています。さらに、地球温暖化の要因となるCO₂やN₂Oの削減に取り組むマメ科植物の一つとして、研究が進められています。 豆発酵食品「醸豆(JYOZ/ジョウズ」を開発・製造・販売する「ハッコウホールディングス」とルピナス豆の研究を行っている、東北大学大学院の佐藤修正教授と番場大助教にお話を伺いました。

N₂Oを減らす「地球冷却微生物」とは?東北大大学院・南澤特任教授に聞く
豆腐や納豆、味噌、醤油など、日本人の食卓に欠かせない大豆。実は、大豆の根に共生する微生物「根粒菌」が、農業の未来に大きな可能性を秘めていることをご存じでしょうか。世界人口が2050年までに97億人に達するとされる中、食糧生産の拡大に伴う温室効果ガス「一酸化二窒素(N₂O)」の排出が深刻な問題となっています。 N₂OはCO₂の約300倍もの温暖化効果を持ち、気候変動対策の大きな課題です。N₂Oの排出量が最も多いのが農業。農業由来のN₂O排出量は、人の活動による排出量の6割を占めるとされています。この問題に挑むのが、東北大学大学院の南澤究特任教授。根粒菌など微生物の力を活用し、農業由来のN₂O排出を削減する最前線の研究についてお話を伺います。
N₂Oを減らす「地球冷却微生物」とは?東北大大学院・南澤特任教授に聞く
豆腐や納豆、味噌、醤油など、日本人の食卓に欠かせない大豆。実は、大豆の根に共生する微生物「根粒菌」が、農業の未来に大きな可能性を秘めていることをご存じでしょうか。世界人口が2050年までに97億人に達するとされる中、食糧生産の拡大に伴う温室効果ガス「一酸化二窒素(N₂O)」の排出が深刻な問題となっています。 N₂OはCO₂の約300倍もの温暖化効果を持ち、気候変動対策の大きな課題です。N₂Oの排出量が最も多いのが農業。農業由来のN₂O排出量は、人の活動による排出量の6割を占めるとされています。この問題に挑むのが、東北大学大学院の南澤究特任教授。根粒菌など微生物の力を活用し、農業由来のN₂O排出を削減する最前線の研究についてお話を伺います。