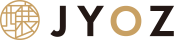豆腐や納豆、味噌、醤油など、日本人の食卓に欠かせない大豆。実は、大豆の根に共生する微生物「根粒菌」が、農業の未来に大きな可能性を秘めていることをご存じでしょうか。世界人口が2050年までに97億人に達するとされる中、食糧生産の拡大に伴う温室効果ガス「一酸化二窒素(N₂O)」の排出が深刻な問題となっています。
N₂OはCO₂の約300倍もの温暖化効果を持ち、気候変動対策の大きな課題です。N₂Oの排出量が最も多いのが農業。農業由来のN₂O排出量は、人の活動による排出量の6割を占めるとされています。この問題に挑むのが、東北大学大学院の南澤究特任教授。根粒菌など微生物の力を活用し、農業由来のN₂O排出を削減する最前線の研究についてお話を伺います。
N₂Oを減らす「地球冷却微生物」とは?
南澤特任教授のチームは、マメ科植物の根に共生する微生物「根粒菌」がN₂Oを分解する能力を持つことを発見しました。2013年には、大豆畑で試験的に繁殖させ、N₂Oの排出を約3割削減することに成功しています(Itakura et al. 2013)。
--南澤教授が今取り組んでいるプロジェクトについて教えてください。
南澤特任教授(以下、南澤):化学肥料には、農作物の育ちをよくする窒素化合物が含まれています。窒素化合物が土の中で分解されると、N₂Oに変化し、大気中に放出されるのですが、N₂Oを分解して無害な窒素ガス(N₂)に還元して温室効果ガスを減らす微生物を根粒菌の中から発見しました。
--「地球冷却微生物」と呼んでいるそうですね。記事で読みました。
南澤:そうです。そして、最近になってN₂O削減能力が特に高い菌を見つけました(Wasai-Hara et al. 2023)。その菌を使って、農家さんの畑で実際にN₂Oの排出を減らせるかを試験中です。日本全国の土壌を使った試験も進行中で、生産者の協力を得ながら進めています。民間企業のハッコウホールディングスさんにも協力いただき、良い結果が出つつ あります 。


(写真:大豆収穫前後の畑でのN₂O計測の様子)
N₂Oは、根粒が腐る際に発生することが知られていますが、同時に根粒菌がN₂Oを分解することも分かっています。その研究がベースにあって、温室効果ガスを減らす仕組みを強化することでN₂Oガスが減るのでは? と仮定してそのメカニズムを解明し、根粒菌の研究を進めてきました。N₂Oを化学物質で減らすのではなく、微生物を使うという手法は世界初です(Sánchez & Minamisawa 2019)。

(写真:N₂O計測の様子)
そんな中、メタン発酵消化液を活用するやり方も 北欧の研究者によって発見されました(Hiis et al. 2024)。メタン発酵では生ゴミや野菜からメタンガスを発生させて発電に使いますが、発酵後の消化液を肥料として利用する際にN₂Oが発生します。北欧の研究者が、このN₂O排出を抑える微生物を探し出す研究に20年かけて取り組み、ついに土壌や消化液の両方で増殖可能な菌を発見しました。
さらに、市民の方にも協力を仰ぎ、土壌に含まれる微生物の分析やN2O排出量の測定を進めています。これまでに約30株の有望な微生物を分離しており、農業からの温室効果ガス削減に活用する計画を進めています。
2050年までに農地由来の温室効果ガス80%削減を目指す
--南澤教授がプロジェクトリーダーを務めている東北大のプロジェクトでは、2050年までに農地由来の温室効果ガスの80%削減を実現することを目的としているそうですね。
南澤:2029年までには半分削減したいと考えています。微生物の資材を使ったところではN₂Oの発生を半分にしたい。それを世界に普及させる。そんな社会実装のための雛形を作ることを目標にしています。プロトタイプを作って実際やってみたらダメだったというのでは困るので、今から実証実験をしてデータをたくさん蓄積していく必要があります。
--今後の研究について伺いたいのですが、先生の関心はどのような方向性にありますか?
南澤:研究を進める中で課題になるのが、土着菌の存在です。例えばアメリカでは100年以上前から大豆栽培が行われており、初期に混入した菌が優勢になっています。この「土着菌」は外来の有益な菌と競争し、接種菌(有用菌)が効果を発揮できない場合があります。この問題を「競合問題」と呼び、これを克服するための研究が進められています。
具体的には、大豆や菌の遺伝子を改良し、両者の相性を高める技術の開発に取り組んでいます。また、接種した菌の動態についても研究しています。例えば、接種した菌が土壌にどの程度定着するのか、毎年の接種が必要なのか、一度の接種で十分なのかといった点です。さらに、菌が自然環境でどのように影響を受けるのかを調べることも重要です。
これらの研究は、基礎的な微生物学と農業の応用研究の両面に関わっています。具体的な課題を解決しながら、基礎研究と結びつけて進めていく必要があります。