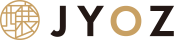痩せた土地でも力強く育つルピナス豆。地中海沿岸地方と南北アメリカ、南アフリカなどに200種以上が分布する豆で、ハッコウホールディングス社が日本で初めて、ルピナス豆の低アルカロイド品種の開発に成功しました。大豆と同等のタンパク質量を有する一方で、窒素肥料がほとんど不要というだけでなく、大豆の3分の1という非常に少ない水の量で育つという特性を持ち、大豆特有の臭み・クセがなく、大豆アレルギーのアレルゲンを持たないため多くの大豆製品の代替としても活用できるとして期待されています。
前編に引き続き、東北大学大学院の佐藤修正教授に、ルピナス豆の可能性についてお話を伺いました。
ルピナス豆が痩せた土地で育つ理由
--大豆の代替としても注目されているルピナス豆ですが、ルピナス豆の特長を教えてください。
佐藤修正教授(佐藤):ルピナス豆は、根粒菌と共生して窒素固定を行うため、窒素肥料が不要です。それに加えて、もう一つ重要な点があります。他のマメ科植物や多くの陸上植物は、「菌根菌」と呼ばれる真菌類の仲間と共生しています。菌根菌は、植物が陸上に進出した初期の段階で水やリンの吸収を助ける役割を果たしていました。
ところが、ルピナス豆は進化の過程で何らかの理由で菌根菌との共生能力を失ってしまいました。そのため、リンの吸収能力が低下してしまったのです。しかし、それに適応するために特殊な根の形態を進化させました。ルピナス豆はリンが不足すると「クラスタールート」と呼ばれる根をたくさん発達させる能力を持っています。この特殊な能力のおかげで、リンが少ない土壌でも生育できるようになったのです。そのため、肥料を与えないほうが元気に育つという特性があります。
--だから、痩せた土地でも育つ?
佐藤:痩せた土地のほうがむしろ適しています。無駄に肥料を与えると、ルピナス豆本来のポテンシャルを発揮できなくなる場合もあります。そういう意味で、ルピナス豆はこれからの社会にとても役立つ植物だと思います。肥料を減らし、化学肥料に頼らないで食料を生産するうえで非常に重要な植物です。
そして、ルピナス豆はタンパク質が豊富です。さらに、大豆より脂質や糖分の量が少ないという特徴もあります。大豆の場合、タンパク質と脂質の間にトレードオフの関係があり、タンパク質を増やすと脂質が減り、脂質を増やすとタンパク質が減る、というような性質があります。そのため、どちらも一定量含まれてしまいますが、ルピナス豆は基本的にタンパク質に寄った構成になっています。
ですから、タンパク質だけを摂取したい、あるいはタンパク源として利用したい場合には、大豆よりもルピナス豆のほうが利用価値が高いと言えます。特に脂質や糖分の摂りすぎが懸念される現代の食生活では、ルピナス豆が持つポテンシャルは非常に大きいと思います。

(写真:東北大学大学院の佐藤修正教授)
日本の風土に合ったルピナス豆はできる?
--前回、日本でもルピナス豆の実験に着手されているというお話でしたが、ルピナス豆の栽培は日本では難しいのかなと思いました。
佐藤:そこが、おそらく一番乗り越えなければならないポイントだと思います。特に湿度、土壌の湿度の問題が日本での栽培に大きく影響するのではないかと考えています。ただし、育種を進めていく中で、日本の環境に適したルピナス豆を作り出せる可能性は十分あると思っています。
--日本の風土に合ったルピナス豆を作るということですね。
佐藤:そうですね。掛け合わせを行うことで、子孫の中に多様性が生まれます。異なる来歴を持つ二つの親を掛け合わせると、その子どもたちには親の特徴がさまざまな形で混ざり、バリエーションが出てきます。その中で、日本の環境に適した強い性質を持った個体が現れる可能性があります。
さらにその選抜を進め、良い特徴を持つ子どもたちをさらに掛け合わせていくことで、より日本の栽培環境に適したルピナス豆を作り出せるのです。これまでの育種では、こうした選抜作業は経験や勘に頼る部分が大きかったのですが、今回のプロジェクトでは親のゲノム情報をすべて明らかにし、それを活用した育種を行おうとしています。
具体的には、親のどの特徴がどのように違うかを事前に把握し、その情報をもとに子どもたちがどの特徴を引き継いでいるのかを分析します。そして、よく育った個体を調べると、「この親のこの特徴と、もう一方の親のこの特徴を併せ持つと良い結果が出る」というパターンが見えてきます。このような情報を基に、さらに良い特徴を持つ個体を選んでいくのです。こうした戦略をガイドライン付きで進めるためのゲノム情報基盤を作ることが、今回のプロジェクトの目的です。
--だから佐藤教授の専門であるゲノム解析が鍵になるんですね。
佐藤:これまで日本では、ルピナス豆を特に食用として活用する意識で掛け合わせや選抜を行うことはほとんどなかったと思います。主に緑肥や家畜飼料として利用されてきたため、食用として真剣に取り組むという発想がなかったんですよね。でも、食用としての視点でルピナス豆を育てることには、大きな可能性があると思います。
--特に食料危機が懸念される中で、改革の一つとして期待されます。
佐藤:これからは循環型や環境配慮型の農業が求められる時代です。ルピナス豆は、その先導役になれる植物だと思います。日本でも十分取り入れられる可能性があると思いますし、それに加えて、ハッコウホールディングさんのようにルピナス豆を発酵させる技術を持っているのは非常に強みですね。
ルピナス豆を食用にする際の課題としてはアルカロイドの問題があります。アルカロイドの量は品種間で差がありますが、完全にゼロにすることは難しい。アルカロイドは植物が生きていくために必要な要素でもあるためです。ただ、アラネア発酵の技術を使えば、微生物の力でアルカロイドを削減できることが科学的に証明されています。この技術を持ちながらルピナス豆の栽培を進めるというのは非常に良いアプローチだと思います。
--発酵食品としての「醸豆 テンペスト」にも注目されますね。
佐藤:「醸豆 テンペスト」はまだ日本では普及していない部分もありますが、発酵食品としてのポテンシャルは非常に高いです。発酵過程で微生物がもたらすビタミンやミネラルを摂取できる点でも、健康志向の食生活に合っています。豆そのものを食べるよりも、発酵を活用することでルピナス豆のポテンシャルをさらに引き出せると思います。
ヨーロッパではビーガンやベジタリアンの間で植物性タンパク質の需要が高まっていますが、ルピナス豆が持つポテンシャルは非常に大きいです。このムーブメントに日本も取り組み、日本で栽培したルピナス豆を活用した商品を開発できれば、耕作放棄地などの活用にもつながると思います。ルピナス豆は、地力が低い土地ほどそのポテンシャルを発揮する植物なので、日本の農業を支える重要な作物として役立つ可能性があります。
持続可能な農業のために…ルピナス豆の役割とは?
--基礎研究や食材の多様性がもたらす効果には非常に期待していますが、研究者としてどのようなイメージをお持ちですか?
佐藤:現在の研究では、温室効果ガスの削減をテーマとするプロジェクトに取り組んでいます。農業活動による温室効果ガスの排出をいかに減らすかが重要な課題です。その対策の一つとして、化学肥料のインプットを減らすことが、今後の農業にとって重要だと考えています。
ルピナス豆のポテンシャルは、窒素固定の能力だけではありません。大豆などではリン肥料が必要ですが、ルピナス豆はリン肥料がほとんど不要です。そのため、人工肥料を使用しなくても栽培できる可能性があります。収量は多少落ちるかもしれませんが、それでも持続可能な農業の一環としてペイできる作物になると思います。
さらに、ルピナス豆を栽培した後、土壌に残る窒素分を利用して他の作物を栽培することで、肥料を使わない農業サイクルを構築できる可能性があります。こうした波及効果を考えると、ルピナス豆の活用は非常に大きな意義を持つと思います。
--食物繊維やセルロースの観点ではどうでしょうか?
佐藤:ルピナス豆は、食物繊維やセルロースが非常に豊富です。豆をそのまま食べるだけでも摂取量が増えますし、発酵によってその効果がさらに高まる可能性があります。そうした特性も含めて成分分析を進め、どのような品種が食用として普及しやすいかを検討する必要があると思います。
--どちらに重点を置くかは、関係者で相談して進める形でしょうか?
佐藤:はい。栽培特性を重視するか、豆の特性に重点を置くかで方向性が変わります。ただ、どちらに進むにしても、ゲノム解析によって得られる目印が役立つはずです。その目印を基に、両方の良い特性を合わせ持った品種を選抜していく戦略が可能だと期待しています。