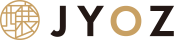心身を健やかに導いてくれるヘルシーフード。自分の食生活においしく無理なく取り入れて、継続的に付き合うことができたらうれしいですよね。そうは言っても、仕事、家事、育児、趣味などをこなす忙しい日々であれば、理想通りにはなかなかいかないときもあります。「料理を作る時間がない」「作るのが億劫」と感じることがあってもおかしくはありません。
そこで今回は、新しい発酵食品として注目されている「醸豆 テンペスト」を使いこなして、作り置きおかずをご提案してみたいと思います。定期購入やまとめ買いでストックしてある醸豆 テンペストの賢い消費術とは?
「醸豆 テンペスト」とは?

(写真:「醸豆 テンペスト」)
「醸豆 テンペスト」は、アラネア発酵という革新的な技術によって作られる植物性の発酵食品。豆由来のたんぱく質や食物繊維が豊富に含まれています。その他栄養面でのメリットも多く、蒸し大豆と比べて遊離アミノ酸総量が6.75倍、遊離グルタミン酸は10.67倍、ビタミンB6は71.31倍に増えているのも魅力。
また、塩を使わない無塩発酵で作られるので、発酵時に大量の塩を使用する一般的な発酵とは異なり、食塩相当量は0.28g(100gあたり)という安心感もあります。(※)さらには、シート状で冷凍保存ができるため、おいしくて活用度の高い代替肉を探している人にはピッタリです。
※ 2024年11月 食品分析センター調べ
「醸豆 テンペスト」の余った分を使って、ヘルシーな肉おかずに大変身!

(写真:ひき肉と「醸豆 テンペスト」)
醸豆 テンペストの1袋の容量は225g。醸豆 テンペストに限らず、食材を使ったあとに残ってしまうことはよくあること。または、1袋まるまる使い、ボリューム感のあるおかずを作ってストックしておきたいというときも。ここではそのようなニーズを満たすレシピを考えました。ポイントはひとつ。醸豆 テンペストをひき肉と合わせて肉料理のヘルシー度を上げることです。
コツは、醸豆 テンペストの重量に対して、ひき肉を同量〜2倍の量で合わせることです。ひき肉は豚肉でも鶏肉でも好きなものを選びましょう。ひき肉と醸豆 テンペストがおいしくまとまる秘訣は、焼肉のたれ。加えることで食材の個性が見事に融合し、食べ応え満点のハンバーグに仕上がります。醸豆 テンペストを合わせることで、いつものハンバーグの食感や風味に深みが生まれ、旨味の相乗効果も期待できます。それでは早速、「ミート!ミート!ハンバーグ」を作っていきましょう。
ミート!ミート!ハンバーグ

(写真:ミート!ミート!ハンバーグ)
材料(醸豆 テンペスト 1袋分)
※使いたい醸豆 テンペストの量で全体調整をする
| 醸豆 テンペスト | 1袋(225g) |
| ひき肉※ | 225g~450g |
| 刻みねぎ | 大さじ2~4 |
| 焼肉のたれ | 大さじ2~4 |
| 粉チーズ | 大さじ1~2 |
| こしょう | 適宜 |
| 全卵 | 1~2個 |
| (仕上げ用) | |
| てりやきのたれ(焼肉のたれでも可) | 適宜 |
| 卵黄 | 人数分 |
| 付け合わせ野菜(豆苗など) | 適宜 |
※肉感をしっかり味わいたい場合は、ひき肉を醸豆 テンペスト2倍量の450gにする。2倍量の場合、ほか材料は記載の最大値を採用する。
作り方
Step 1
「醸豆 テンペスト」を手で細かくつぶしてひき肉状にする。大きめのボウルにひき肉、ねぎ、全卵、焼肉のタレ、粉チーズ、こしょうと合わせて良く混ぜ合わせる。
Step 2
ハンバーグ上に成形して熱したフライパンで焼く。はじめに1~2分焼いたらひっくり返して、弱火にしてフタをして5分焼く。仕上げにてりやきのたれを絡める。器にハンバーグを盛り付け、卵黄と野菜を添える。
※冷蔵庫保存で1週間程度、冷凍保存で1か月程度保存可能。
【その他アレンジ】

・枝豆を加える
・カレー粉を隠し味に加える
・ミートボール状にしてつくね焼き鳥、お弁当おかずに
ストック買いや大量消費用途としてもオススメ!
このハンバーグは、醸豆 テンペストをおいしく食べ切りたい、まとめて料理しておいて少しずつ食べたいといったニーズをしっかり満たしてくれます。
例えばまとめて買って一度に作り置いておけば、いざというときの頼れる肉おかずとして活躍してくれます。また定期購入をして中途半端な量が余っている方にも、肉や他材料の調整がしやすいので作りやすいごちそう料理と言えます。忙しい時こそ、ヘルシーでボリューム満点の肉おかずがすぐに食べられたら最高です!